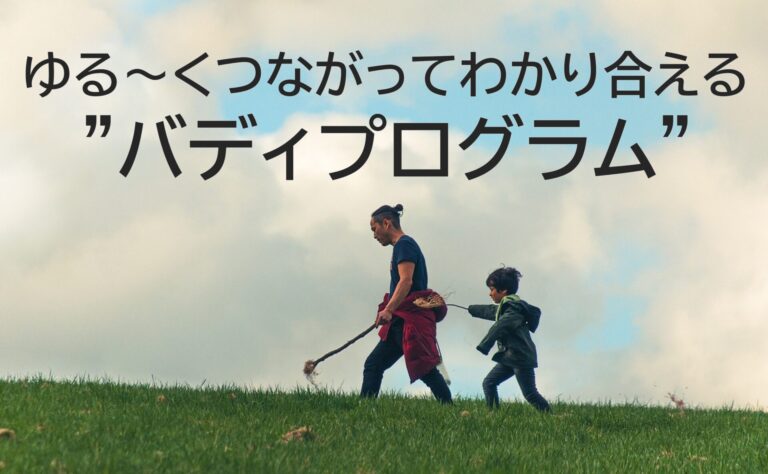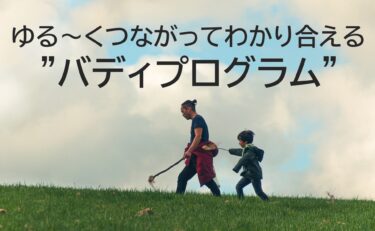1.バディプログラムとは
バディプログラムの「バディ」とは”仲間や親友”という意味で、バディプログラムは友達づくりの仕組みと言えるでしょう。
現代において、孤独が多くの場面で問題になっています。ひきこもり、若者や高齢者の単身者、孤独死なども数多くニュースで取り上げられています。その理由の一つに、本当に分かり合える友達やパートナーがひとりもいないということが挙げられます。その孤独感を減らし、世代を超えて友達としてあるいは仲間として、コミュニケーションを増やしていこうというのが、この”バディプログラム”なのです。ちょっと難しくいうと、バディプログラムは異なる背景を持つ者同士が”バディ(仲間・親友)”となり、互いをサポートし、共に成長しようということです。
簡単にいうと「ゆる~くつながっていくことで、分かり合えるようになろう」という感じです。

2.バディプログラムの起源と発展
バディプログラムの起源は、1980年代のオランダに遡ります。当時、精神疾患がある人々の社会参加を促進するため、地域住民らが、彼らをサポートする活動が始まりました。この活動は、精神疾患がある人の孤立を防ぎ、社会参加を促進する上で大きな助けとなりました。加えて、地域住民の精神疾患に対する理解も深めることにもつながりました。つまり、支援する人も支援される人も、同じ一人の人間として対等であり、仲間(バディ)なのだ、ということが心の支えになっていったのです。
その後、バディプログラムは、障がい者、高齢者、外国人など、様々な社会的な弱者を対象とした支援活動へと発展しました。現在では、欧州を中心に、教育機関や企業、NPO法人など、様々な組織がバディプログラムを導入し、多様性を尊重する社会の実現に貢献しています。
日本では、2020年に”We are Buddies”(私たちは仲間だ)という市民団体が立ち上がり、活動が始まっています。ここ長野市でも、市民活動として2023年に取り組みが始まったばかりです。このプログラムには、公立大学法人長野県立大学の理事長裁量経費採択事業として長野県立大学の支援を受けて活動を開始しています。

3.バディプログラムの仕組み
バディプログラムの基本的な仕組みは、支援を必要とする人と、支援を提供する意思のある人が2人組になって、定期的に交流するというものです。この2人組のことを「バディズ」と呼んでいます。
長野市でおこなっている”バディプログラム”は、子ども(5~18歳)と大学生や大人が2人組になり、毎月2回程度会って、遊んだりお話したりします。つまり、まったく世代がちがう2人が対等な立場で会って、遊びや会話を通して、少しづつ信頼関係を作っていき、お互いの本当の気持ちを出していくのです。
この関係には、親や兄弟、学校の友達などの利害関係がないので、いわゆる”空気”を読む必要がありません。「こんなことを言ったら、お母さんが怒るんじゃないか」「これをしたら友達から仲間外れをされるんじゃないか」というような、”空気”を読む必要がない、ということなのです。まったく利害関係のない他人だからこそ、”空気”を読んで忖度(そんたく)する必要がないからこそ、自分の気持ちに素直に表現できるのです。
忖度(そんたく)
忖度とは、相手の考えや意図を、相手がはっきりと言わなくても自分から読み取ろうとする行為や考えをもつこと。
大切な子どもを知らない大人と会わせるなんて「変な人だったらイヤだな」「変なことをされるんじゃないか」といった不安がありますよね。このバディプログラムに参加する大人は”おとなバディ”と呼ばれ、すべて紹介制で、運営メンバーから認可されてトレーニングを受けた人にしかなれません。そして、”おとなバディ”と”こどもバディ”の組み合わせは、慎重に時間をかけてこのバディズ(2人組)をつくっていきます。そして、2人組ができた後、会う場所は2人で決めます。公園や動物園、カフェなど密室でない公共の場であれば、どこでもOKです。会っていく中で「ちょっと合わないな」などの問題が発生した場合には、運営メンバーが責任をもって対応します。月2回程度を1年以上続けていくことが、基本となります。信頼関係をつくるには、何回も会って、ゆっくり話していくという時間がどうしても必要なのです。
このプログラムの参加料は”おとなバディ”も”こどもバディ”も、両方とも無料で、遊ぶときに使う活動費は支給されます。

4.バディプログラムの現代における必要性
人はさまざまな悩みをいつも抱えています。その悩みのなかで、もっとも強くありながら、もっとも外からわかりにくい悩みの一つが「こころの孤独感」です。自分のこころの中にあるがなんとなく言葉にできない「もやもや」したものや、言葉にはできるけど誰にも言えない気持ち、これから先にどうなるのだろうかという不安な気持ち、などが頭のなかをぐるぐると回っているのです。親はいるけど、学校の友達はいるけど、なんとなく孤独を感じてしまう。孤独という”空気”が自分の周りに漂っている感じがするのです。
特に、現代の子どもたちは話されている言葉ではなく”空気”を先読みします。心理学的には「ダブルバインド」と呼ばれています。不登校の例でいくと、親は「つらかったら学校に行かなくてもいいんだよ~」と言っているが、その表情は「絶対に学校に行きなさい!」という雰囲気を出している、ということがあります。相反するメッセージを同時に発信していることになります。すると、子どもは混乱し、結果的に親に忖度します。「つらくても学校に行けってことでしょう‼」というメッセージを受け取ることになるのです。
このように、子どもは自分の本当の気持ちを封印して、”空気”を読むことをずっと強要され続けられているのです。そして、この本当の気持ちを上手にカモフラージュして、外からわからないようにしている。これが、孤独という”空気”を生み出しているのです。
このバディプログラムは、この孤独感を持つ”子どもバディ”を支援することが基本となっています。一方、支援する大人”おとなバディ”にも多くのメリットをもたらします。大人も悩みながらもさまざまな人生を経験してきており、成長してきました。学業や仕事、子育てなどその時々の悩みは絶えませんが、なんとか生きてこれたのです。
そんな時、ふと感じるのは若い世代との感じ方の違いです。いわゆるZ世代とかX世代と呼ばれる現在のデジタルネイティブの子どもたちとの解離を感じています。ゲームやインターネットが生まれたときから身近に存在して、YoutubeやX(旧ツイッター)、インスタグラム、スマホなどをすばやく自由自在に操れる世代とは、孤独感のイメージ自体が異なるのです。
そのような子どもの孤独感のイメージを聞き、理解しようとするプロセス自体が、おとなの孤独感も解消してくれるのです。「こんなことに興味があるんだ」「こんなことに悩んでいるんだ」などを、聞くことによって、大人の心の中にある「もやもや」感に現代にはびこる孤独の空気感の霧が晴れていきます。ここで、大人はすぐアドバイスをしたがるのですが、アドバイスをすることをちょっと我慢し「聞くこと」に徹することで、”子どもバディ”の気持ちがだんだんとわかってくるのです。
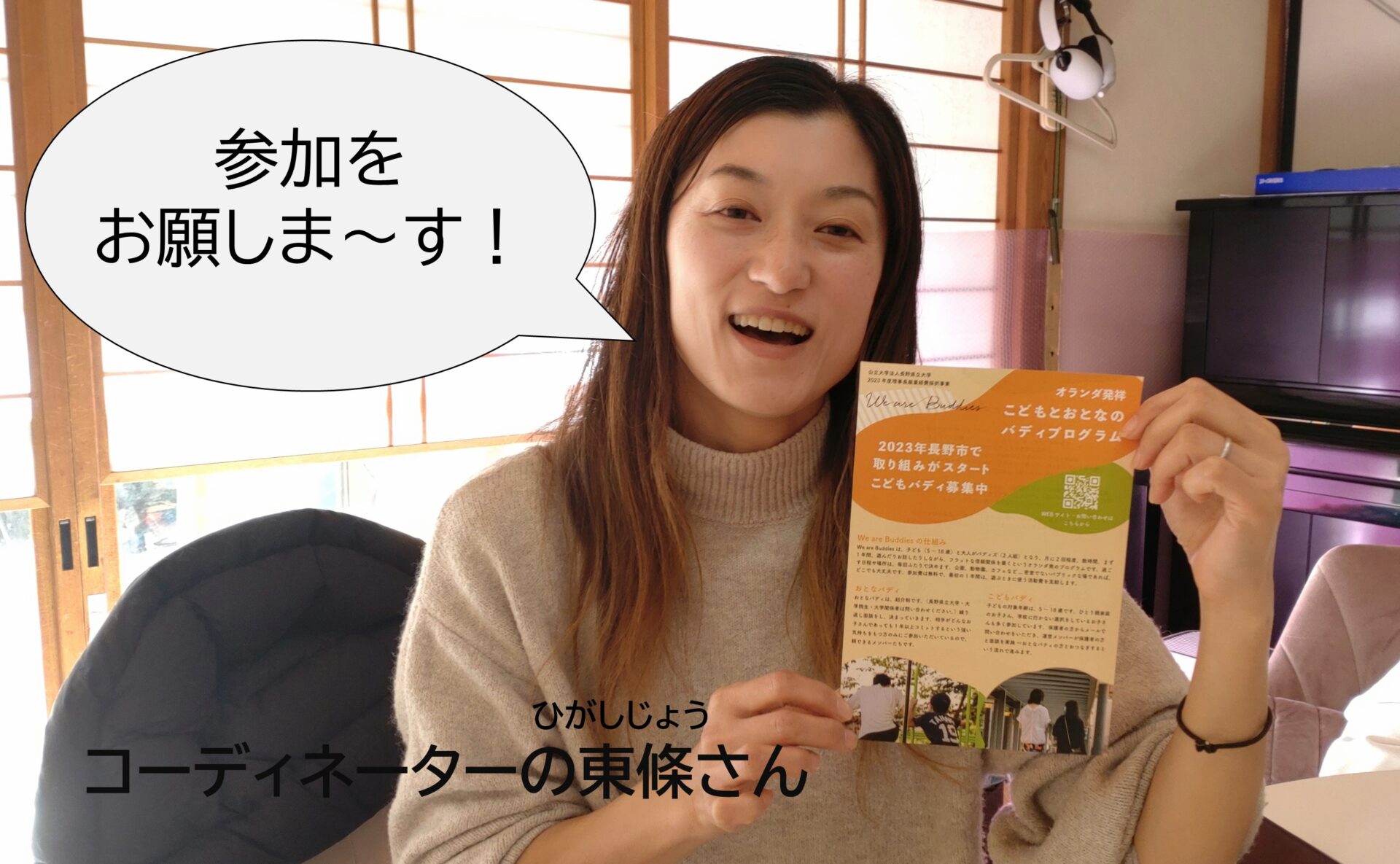
5.バディプログラムに参加するには
実際にバディプログラムに参加するには、大人バディとこどもバディでは、少し異なります。
・おとなバディの参加方法
おとなバディに参加するには、紹介制なので地域ごとにコーディネーターがいます。まずは、その方とつながります。そして、コーディネーターと繰り返し面談し、その方が本当に大人バディとして適した人なのかを判断します。トレーニングも行いますし、その紹介者との関係なども判断材料になります。最終的には、本部である”We are Buddies”からの認可を得てから、マッチングがスタートします。
・こどもバディの参加方法
こどもバディに参加する対象年齢は、5~18歳です。保護者からメールで問い合わせをして、コーディネーターが保護者と面談をします。そして、おとなバディとマッチングがスタートします。マッチングには、こどもの意見を尊重しながら、慎重に進めていき、「この人だったらいいな」という気持ちを大事にします。基本的には、同性のバディズをイメージしています。参加費は無料です。
「We are Buddies」のウェブサイト
https://wearebuddies.net/

6.今後の展望:誰もが活躍できる社会へ
バディプログラムは、多様性を尊重し、誰もが活躍できる社会を実現するための有効な手段の一つです。今後は、日本全国において、様々な背景を持つ人々が交流し、互いをサポートし合うバディプログラムを推進していく必要があると考えています。
そのためには、バディプログラムの運営ノウハウを共有し、バディ同士のマッチングや研修プログラムをさらに充実させること重要です。また、企業や教育機関、NPOなどが連携し、地域社会全体でバディプログラムを経済的に支える体制を構築する必要があります。その活動資金のための寄付をお願いしています。

7.まとめ
今回は、バディプログラムについて解説しました。バディプログラムの仕組みは、支援を必要とする人と、支援を提供する意思のある人が2人組になって、定期的に交流するというものです。その起源は、1980年代のオランダで、精神疾患がある人々の社会参加を促進するために、地域住民主導で始まりました。そして、日本でも2020年にバディプログラムが始まっています。これは、多様性を尊重し、誰もが活躍できる社会を実現するための有効な手段です。おとなバディに参加するには、少し条件がありますし、こどもバディに参加するには保護者の同意が必要となります。この長野においても、2023年にバディプログラムの取り組みが始まっています。
このブログ記事がバディプログラムへの理解を深め、多くの方々がバディプログラムに参加するきっかけとなることを願っています。
以上、「ゆる~くつながってわかり合える”バディプログラム”」のご紹介でした。
【参考資料】
・オランダ発祥 こどもとおとなのバディプログラム 2023年長野市で取り組みがスタートこどもバディ募集中
・We are Buddies ホームページ https://wearebuddies.net/